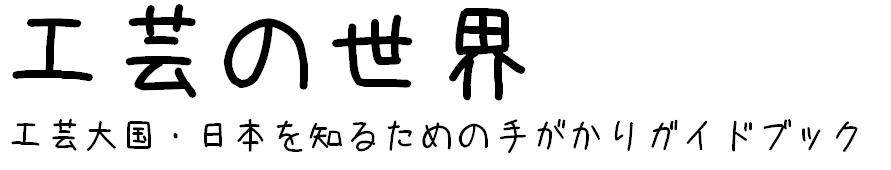top:打ち捨てられた日本の工芸
打ち捨てられた日本の工芸
吾々は日本人であります。それ故日本人としての生活に悦びを抱きます。しかし考えてみますと、吾々が現在用いています品物にどれだけ日本的なものがあるでしょうか。都会の生活などをみますとそれが甚だ乏しくなっているのを気附きます。知らず識らずの間に、余りにも沢山西洋風なものを取り入れて来たからであります。それは明治この方起った著しい変化でありました。
それ以前の日本人はほとんど凡て純粋に日本のものばかりで暮していました。そうしてそれらのものには立派なものが沢山ありましたが、新しい時代では一途に古くさいものと思い込まれました。従ってその値打が軽く見られ、日本的な多くのものを惜気もなく棄て去りました。
もとより明治になって西洋文化を盛に取り入れ、これを熱心に勉強したことは、日本の発達にとって大変役立ったことは申すに及びません。ですが半面に二つの弊をも伴いました。 一つは極端な西洋崇拝に陥る人が沢山出たことであります。二つにはその結果、日本的なものを軽んずる風習がこれに伴ったことであります。これは日本文化にとって由々しき問題ではないでしょうか。
吾々は日本人でありますから、出来るだけ日本的なものを育てるべきだと思います。
丁度支那の国では支那のものを、印度では印度のものを活かすべきなのと同じであります。西洋の模造品や追従品でないもの、即ち故国の特色あるものを作り、またそれで暮すことに誇りを持たねばなりません。たとえ西洋の風を加味したものでも、充分日本で咀疇されたものを尊ばねばなりません。日本人は日本で生れた固有のものを主にして暮すのが至当でありましょう。故国に見るべき品がないなら致し方ありません。しかし幸なことに、まだまだ立派な質を有ったものが各地に色々と残っているのであります。
それを作る工人たちも少くはありません。技術もまた相当に保たれているのであります。ただ残念なことに前にも述べた通り、それらのものの値打ちを見てくれる人が少くなったため、日本的なものはかえって等閑にされたままであります。誰からも遅れたものに思われて、細々とその仕事を続けているような状態であります。それ故今後何かの道でこれを保護しない限り、取り返しのつかぬ損失が来ると思われます。それらのものに再び固有の美しさを認め、伝統の価値を見直し、それらを健全なものに育てることこそ、今の日本人に課せられた重い使命だと信じます。
【引用】柳宗悦(著)(1985)「手仕事の日本」岩波書店